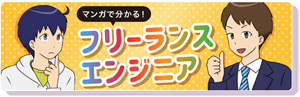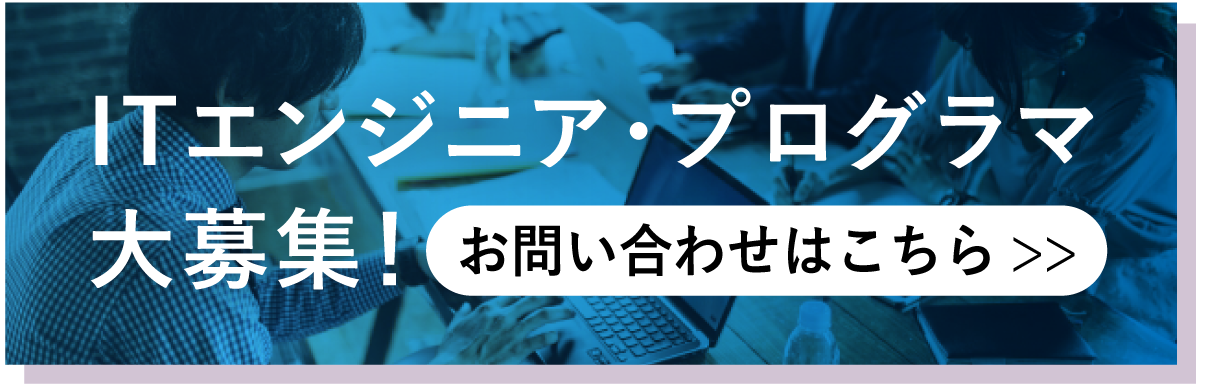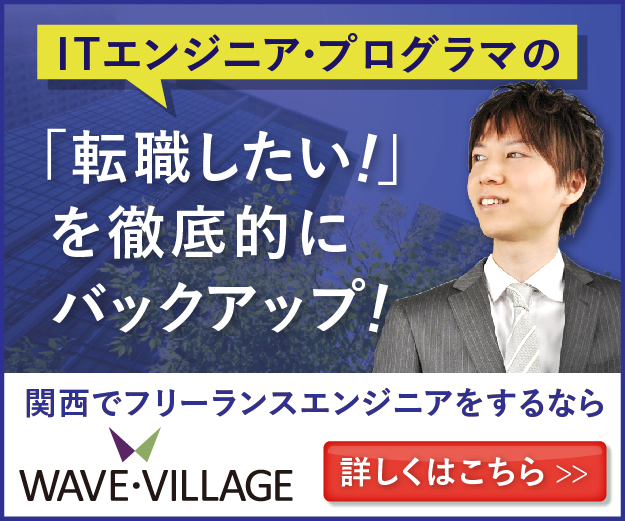【全社員がAIを使える組織へ】2027年度までに全社員をAI人財にするNTTデータの本気

生成AIが社会のあらゆる領域で存在感を高める中、「人がどのようにAIを活用するか」が、企業競争力の鍵になりつつあります。そんな中、NTTデータグループは2025年10月、グローバル全社員を対象にした大規模な生成AI人財育成計画を発表しました。目標は、2027年度までに約20万人の全社員が生成AIを実践的に活用できるようにすることです。この取り組みは、単なる社内研修の拡大ではなく、AI時代にふさわしい企業文化への転換を目指す「全社員AIネイティブ化」プロジェクトと言えます。
【取り組みの背景】 AIがもたらす変革の波

生成AIは、ソフトウェア開発やデータ分析だけでなく、コンサルティング、営業、デザインなど、あらゆる分野の仕事に影響を与えています。一方で、「どう使えば成果につながるのか」「倫理的・安全に利用するには?」といった課題も多く、技術だけでなく人財教育の重要性が増しています。
NTTデータグループは、2023年度から生成AIの実践的な活用を全社的に推進してきました。社内ではすでに生成AIを使った業務効率化や開発支援ツールが広く導入されており、その成果をさらに拡大するための基盤として「人財育成」を次のフェーズに位置づけています。
3万人から7万人、そして20万人へ ── 加速する育成ロードマップ
NTTデータグループは2024年10月から、全社員を対象とした生成AI人財育成プログラムを開始しました。当初は2026年度末までに3万人の育成を目標としていましたが、2025年10月時点ですでに7万人が修了。わずか1年で目標を大きく上回る成果を上げました。これを受け、同社は新たに2027年度までに全社員約20万人を対象とする拡大計画を発表しました。グローバル全拠点で共通の育成体系を整備し、職種・地域を問わず同水準のAIリテラシーを確立する方針です。
スキル体系:4段階の「生成AI人財レベル」
育成プログラムは、社員の業務内容やスキルレベルに応じて4つの段階に分類されています。
■ Whitebelt(ホワイトベルト)
生成AIの基本理解、安全な利用、ガバナンスやセキュリティ知識を学ぶ基礎レベル
■ Yellowbelt(イエローベルト)
生成AIを業務の中で活用し、価値を創出できる実践レベル
■ Greenbelt(グリーンベルト)
プロジェクト全体のAI導入をリードできる上級者レベル
■ Blackbelt(ブラックベルト)
生成AI技術を用いた新規事業やソリューションを開発できる専門家レベル
2025年10月時点で、すでに7万人がYellowbelt認定を取得しており、社内ではAI活用プロジェクトの横展開が進んでいます。
実践重視の研修とグローバル連携

NTTデータグループの育成方針は「知識だけでなく実践で使えるAI人財を育てる」ことです。研修プログラムでは、OpenAIやMicrosoft、Google Cloud、AWSなど主要AIパートナーとの連携により、各種LLM(大規模言語モデル)を活用した演習を実施。社員は実際にツールを触りながら、プロンプト設計、コード生成、ドキュメント要約、顧客提案資料の作成など、具体的な業務シナリオを通して学びます。
さらに、グローバル各拠点では現地言語・業務特性に応じたカリキュラムが展開されており、海外社員も同一基準でスキルを習得できるよう整備が進められています。
すでに2,000件超のAI関連プロジェクトを受注
育成と並行して、NTTデータグループの生成AI関連ビジネスも急拡大しています。2025年10月時点で、グローバル全体で2,000件を超える生成AI関連の受注を記録。社員が自らの業務で培ったAIスキルを、クライアントの課題解決へと応用している点が大きな特徴です。
安全性とガバナンスへの配慮

大規模なAI活用には、情報漏えいリスクや倫理的課題がつきものです。NTTデータグループでは、社内での生成AI利用ガイドラインを整備し、安全な環境下での利用を徹底しています。特に、業務データの扱いやプロンプトの設計において、AIに依存しすぎない「人間中心の判断」を基本方針としています。
また、各国の法規制やデータ保護方針に対応するため、グローバルレベルでのAIガバナンス体制を構築。社内には専門の倫理・セキュリティ委員会が設置され、AI技術の健全な導入を支えています。
【今後の展望】全社員が“AIを使いこなす組織”へ

NTTデータグループは今後、職種別・役割別にAIスキル定義を細分化し、各社員が自分の業務領域でどのようにAIを活かせるかを明確にしていく方針です。また、AI活用プロジェクトの知見を外部企業・自治体へ共有することで、社会全体のデジタル人財育成にも貢献していくとしています。同社の狙いは、AIを特定部署の専門技術ではなく、全社員が日常業務で自然に使いこなす文化として根付かせることです。生成AIが業務支援ツールから“共創パートナー”へ進化する時代、同社の挑戦は企業のあり方そのものを変える可能性を秘めています。
最後に
AIが進化すればするほど、人間の役割は“どう使うか”にシフトします。NTTデータグループの取り組みは、「AIを導入する会社」から「AIを使いこなす人で構成された会社」への変革そのものです。同社が掲げる“人とAIが協働する未来”は、単なる技術戦略ではなく、社員一人ひとりの可能性を引き出す人財戦略でもあります。この先、他の大企業や自治体にも同様の動きが広がれば、日本発の“AI共創文化”が世界に根付くかもしれません。
筆者Y.S