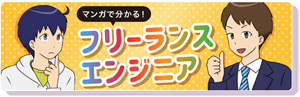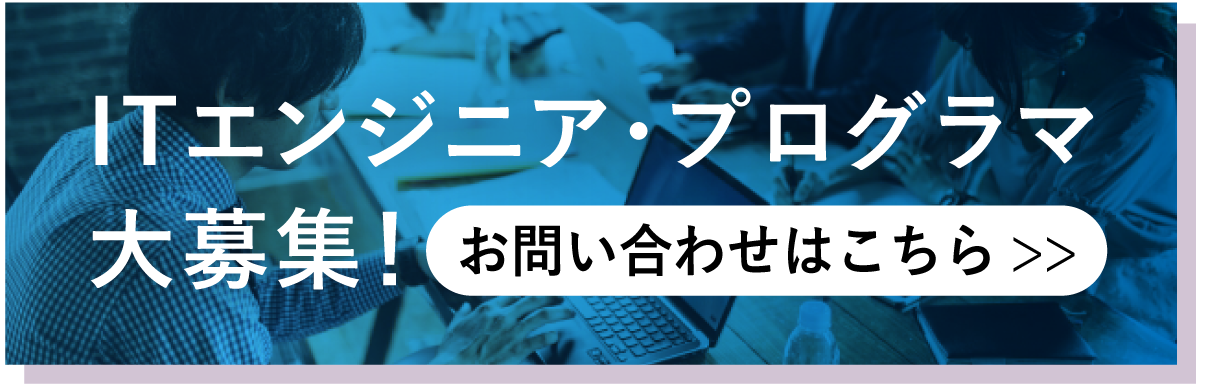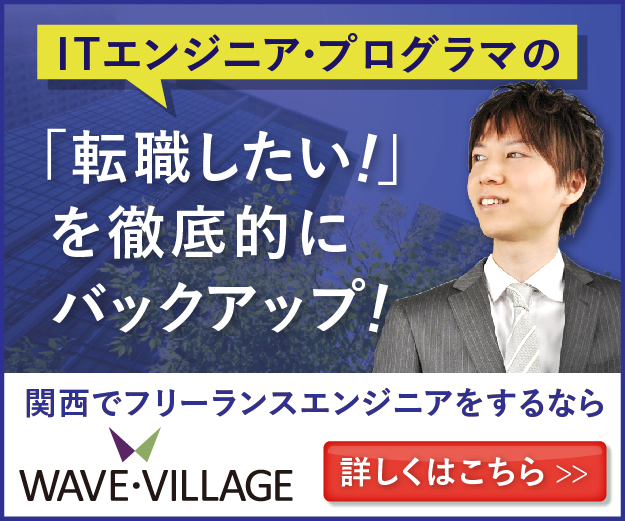次世代行政サービスが始動!newmeが案内する区役所の未来とは?行政DXを支えるアバターロボット
近年、デジタル化の加速に伴い、行政サービスのあり方にも大きな変化が求められています。その中で注目されているのが、アバターロボットを活用した「遠隔区民サービス」です。非対面での対応、バリアフリーな情報提供、多言語への柔軟な対応など、従来の窓口では難しかった課題を解決する新たなアプローチとして、全国の自治体で導入が進んでいます。今回は、東京都大田区で行われた実証実験をはじめ、各地で活躍するアバターロボットの取り組みを紹介しながら、行政サービスの未来について考察していきます。
東京都大田区役所で行われた「遠隔区民サービス」の実証実験

「遠隔区民サービス」とは、物理的に離れた場所にいるオペレーターが、アバターロボットを通じて来庁者とリアルタイムにコミュニケーションを取る仕組みのことです。自治体の窓口業務を遠隔操作で行うことにより、人的負担の軽減と、住民サービスの質の向上を同時に実現できます。
2025年5月にavatarin(アバターイン)株式会社が開発したアバターロボット「newme(ニューミー)」を活用した東京都大田区役所での実証実験の結果が公開され、話題を呼んでいます。この取り組みは、東京都が実施する「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」において採択されたプロジェクトの一環であり、株式会社キャンパスクリエイトの支援のもと、NECネッツエスアイ、電気通信大学の藤井研究室、東芝インフラシステムズと連携して実施されました。実証実験では、本庁舎の窓口にアバターロボットの「newme」を設置し、ローカル5Gと分散アンテナシステム(DAS)を用いて遠隔からの案内業務や多言語対応などの実用性を検証。対面に近い形でサービスを提供し、将来の本格運用に向けた有益な知見が得られました。
アバターロボット「newme」の可能性

(出典:avatarin株式会社 公式サイト)
アバターロボット「newme」は、avatarin株式会社が開発した遠隔操作型ロボットです。タブレット型の顔を持つこのロボットは、インターネットを介して離れた場所から操作者が操作することで、まるでその場にいるかのように人と会話できます。実際に、様々な自治体が「newme」を活用した行政サービスの実証実験を行なっており、住民の利便性向上や業務効率化に貢献できると期待されています。
全国の行政で進められているアバターロボット導入のための実証実験

各地の自治体では、アバターロボットを活用した遠隔行政サービスの実現に向けて、実証実験が積極的に行われています。ここでは、その具体的な事例をいくつかご紹介します。
石川県 小松市
小松市はアバターロボット「newme」を使ったリビングラボ形式の検証に注力しています。令和5年度には「国府ものがたり館(こくぶものがたりかん)」で学芸員による遠隔案内や子ども向けクイズ解説を実施。さらに、成人式実行委員のリモート参加や、JAXA筑波宇宙センターへの遠隔見学など、多岐にわたる用途で実証実験を展開しています。アバターロボットの活用により、障壁を抱える市民も地域文化や教育活動に参加する機会が拡大すると期待されています。
愛媛県 松山市/今治市
愛媛県では、2024年3月に松山空港近くの萬翠荘で「newme」を使った観光案内の実証実験が実施され、遠隔案内の有効性が検証されました。また、今治市では「OriHime」を活用したカフェでの就労体験プログラムを展開し、肢体に障がいのある方がリモートで接客する取り組みを実施。パイロット育成と就労支援の両立を目指しています。
神奈川県 藤沢市
藤沢市では、子どもたちに美術への関心を高めてもらうため、アバターロボット「newme」活用して小学校と辻堂神台にある「藤沢市アートスペース」(FAS)を繋ぎ、美術作品を鑑賞する実証実験が行われました。児童が遠隔操作で展示作品を鑑賞する形式で、現地に行けない子どもたちがロボットを通じて臨場感ある体験を得られる取り組みです。多様な学びの機会を提供し、地方の教育格差を縮める可能性としても高く評価されています。
行政へのアバターロボット導入における課題と展望

アバターロボット導入における課題
アバターロボットの行政サービスへの導入は、まだ始まったばかりの取り組みであり、普及に向けてはいくつかの課題を克服する必要があります。
<導入コストと維持費用>
アバターロボット本体の購入費用や、運用に必要な通信環境、メンテナンス費用などが、自治体にとって負担となる可能性があります。
<技術的な安定性と操作性>
遠隔操作の安定性や、操作を行う職員の習熟度、そして万が一のトラブル発生時の対応などが重要になります。
<住民の理解と利用促進>
アバターロボットという新しいインターフェースに対する住民の理解を深め、積極的に利用してもらうための周知活動が必要です。
<セキュリティとプライバシー>
遠隔操作における映像や音声データの取り扱い、個人情報の保護など、セキュリティ対策を徹底する必要があります。
<法制度の整備>
遠隔での本人確認や、行政手続きの有効性など、関連する法制度の整備が必要となる場合があります。
これらの課題を克服することで、アバターロボットは行政サービスをより身近で、より効率的なものに変革する大きな可能性を秘めています。
アバターロボット導入における今後の展望
今後の展望としては、以下のような点が期待されます。
<技術の高度化>
AI技術との連携により、より自律的な案内や応答が可能になる。触覚フィードバックなど、よりリアルなコミュニケーション体験の実現。
<コストの低減>
量産化や技術革新による導入コストの低下。
<多様な機種の開発>
利用シーンに合わせた、より専門性の高いアバターロボットが登場。
<他サービスとの連携>
オンライン手続きシステムやAIチャットボットなど、既存の行政サービスとの連携強化。
<住民参加型の運用>
住民自身がアバターを操作して地域活動に参加したり、情報を発信したりする新たな活用方法の登場。
アバターロボットは、単なる業務効率化のツールではなく、地域社会におけるコミュニケーションの活性化や、住民一人ひとりのエンパワーメントにも貢献する可能性を秘めていると言えます。
最後に

アバターロボットを活用した遠隔区民サービスは、今後の行政のあり方を大きく変える可能性を秘めています。働き手不足や住民の多様なニーズに応える手段として、アバター技術は非常に有効です。特に「newme」のような実用性の高いロボットは、今後ますます多くの自治体に採用されることでしょう。
導入には課題もありますが、国や自治体の連携によって技術的・制度的な整備が進めば、より多くの住民がこの恩恵を享受できる未来が見えてきます。テクノロジーによって、人に寄り添う行政が実現する時代は、すぐそこまで来ています。
筆者Y.S